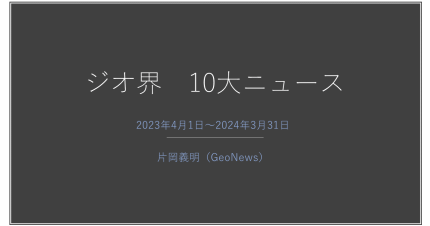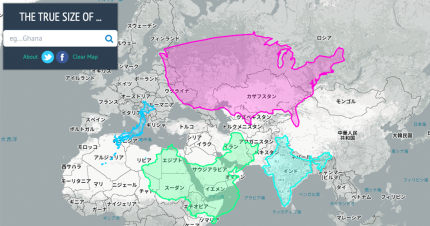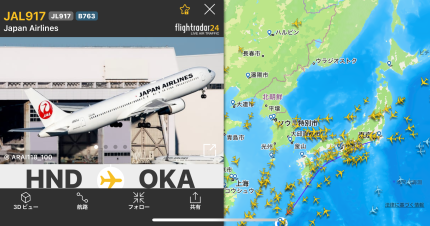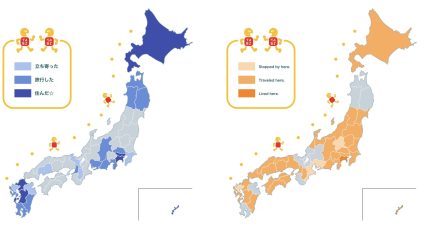【ジオ用語解説】シビックテック
シビックテックとは「シビック(市民)」と「テクノロジー(技術)」をかけ合わせた造語で、市民がテクノロジーを活用して地域の社会課題を解決する取り組みを意味します。
シビックテックはIT技術の進歩にともなって2000年代に米国で始まり、オバマ政権下において、公的機関が保有する情報オープンデータとして公開し、市民がその情報を活用できるようにする機運が高まりました。さらに2009年にはシビックテックの支援コミュニティ「Code for America(CfA)」が設立され、市民が行政と連携しながらIT技術を活用して社会課題の解決や行政サービスの改善に役立てる取り組みが後押しされました。
日本におけるシビックテックの取り組みとしてよく挙げられるのが、2011年の東日本大震災のときに行われたプロジェクト「sinsai.info」です。同プロジェクトでは、ボランティアによって開発された被災地向けの情報サイトが震災発生後わずか数時間後に公開され、被災地の現状や安否情報、避難所の情報などが登録・公開されました。
その後、2013年にはシビックテックの支援コミュニティ「Code for Japan(一般社団法人コード・フォー・ジャパン)」が設立されました。同団体では全国のシビックテックコミュニティの支援や自治体へのITエンジニアの派遣(フェローシップ)などさまざまな取り組みを行っています。
一方、日本各地においてもシビックテックコミュニティが次々と設立され、これらのコミュニティでは地域課題解決など共通のテーマで市民が集まり、アイデアを出し合いながらアプリやサービスを開発したり、オープンデータの整備に取り組んだりと、さまざまな取り組みを行っています。エンジニアだけでなく、調査・研究やデザイン、プロジェクト管理、自治体との連携などさまざまな面で貢献する多様な人が集まり、コミュニティごとにバラエティに富んだ活動をしています。
活動内容としては、ハッカソンやアイデアソン、トークイベント、マッピングパーティー(地図制作イベント)などさまざまです。シビックテックコミュニティによって生み出されたアプリやデータはインターネット上でオープンソースソフトウェアやオープンデータとして公開され、他の地域でも活用されています。
シビックテックが注目されている背景には、社会環境が変化している中で、すべての社会課題の解決を行政に任せておくことが難しくなっているため、市民の力をあわせることで市民参加型の地域社会を実現を図り、行政サービスの向上を図るとともに、オープンデータ活用による新たなビジネスの創出が期待されていることなどが挙げられます。
以下に、これまでシビックテックコミュニティによって生み出された成果の中からいくつか事例を紹介します。
シビックテックコミュニティから生まれた事例
5374.jp
ゴミの収集日を調べられるアプリ。引越などで新しい街に住むことになった際に、このアプリを使えばすぐにわかるようにシンプルなデザインとなっています。一番近いゴミの日とジャンルを色別に表示し、ゴミのジャンルをタップすると捨てられるゴミの一覧を見ることができます。Code for Kanazawaが開発し、金沢市で活用されたほか、全国各地に広がっています。

5374.jp
さっぽろ保育園マップ
札幌市内の保育園を地図上で探せるマップで、Code for Sapporoが開発しました。ソースコードも公開され、利用・再配布を自由に行うことが可能で、札幌市以外の地域でも保育園マップが作成されました。
4919 for Ikoma(食育 for 生駒)
小中学生の給食の献立やカロリー、アレルゲン、栄養バランスなどをスマートフォンで確認できるアプリで、Code for IKOMAが開発しました。生駒市が公開する小学校献立表オープンデータをもとに作成しています。
東京都 コロナウイルス感染症対策サイト
東京都公式の新型コロナウイルス感染症対策サイト。Code for Japanが東京都から受託し、短期間でウェブサイトを構築しました。同サイトのソースコードも公開され、東京都以外の自治体にも活用が広がりました。
能登半島地震コネクトマップ
能登半島地震が発生した際に、インターネットがつながりにくい状況となった被災地において、通信可能な地点を誰でも簡単に登録できるアプリとして公開されました。Code for Kanazawaが開発したもので、登録された情報は「つながる場所マップ」としてインターネット上で公開されました。